
その時、業務が止まった
「ノビ山くんが休んじゃったけど、あの業務どうなってる??
今日入稿なのに……!困った!!」
なんて経験、ありませんか?
僕はありました。たくさんありました。嫌な汗がいっぱい出ました。
こんな困った状況を引き起こす、原因の1つが属人化です。
「属人化」とは何か?
既にご存知の方も多いと思いますが、改めて意味を確認してみましょう。
_________________________________________
ぞくじん‐か【属人化】
企業などにおいて、ある業務を特定の人が担当し、その人にしかやり方が分からない状態になることを意味する表現。
(Weblio辞書より)
__________________________________________________
「その人にしかやり方が分からない状態」、ここではノビ山さんしか業務を把握していなかった状況のことですね。
それで入稿日の今日、突然ノビ山さんが休んで大変困ったことに。
でも、そんな風に特定の人にしかできない業務にこそ意味があると思いませんか?
自分にしかできないからこそ、自分の価値を認めてもらえるというか。
誰にでもできる業務なんて、誰かがやればいいんだから。
そう思ったあなた。それは正しい。とも言える。
この「属人化」、必ずしも悪いことばかりではありません。
世の中には属人化に適さない業務と、属人化に適した業務の2種類が存在します。
否定的な意味で用いられる「悪い属人化」と、目指すべき「良い属人化」について。
今回は「良い属人化」を上手く実現する方法を考えていきましょう。

属人化によるリスク
まず、属人化が引き起こす最悪のケースを一例挙げてみます。
「これは自分にしかできない!」
と無理に業務を続けた結果、体を壊してしまう。
↓
突然の担当者入院。
しかしその人しか業務内容を把握していないので全て中断。
↓
その場しのぎで別の人が対応してなんとか納品。
↓
納期には間に合わせたものの、結局品質不良。
要望を満たしていないため顧客からはクレーム……。
みなさんもこれに近い体験をしたこと、ありませんか?
リスクがあるのは「悪い属人化」
先ほど挙げたようなケースは
・病気療養による人材不足、一部業務の停止
・納期遅延、品質不良によるクレーム、契約違反
など、組織全体に影響を及ぼすリスクを発生させる場合があります。
つまり、属人化が原因となって、組織全体の効率が下がるのが「悪い属人化」です。
「全体の効率」に注目して考えてみてください。

属人化には原因がある
なぜ「悪い属人化」が発生してしまうのか?
こういった状況は、目の前の業務をこなすことばかりに意識が集中している場合に起こりがちです。
ある業務を担当し、実行している最中の個人には、自分のタスクを処理している限り問題はないように見えます。
しかし、ただ現在の仕事をあくせくと消化していくだけでは、トラブル発生前に危うい点に気付き発生前にその芽を摘むなど、細かなところまで気を配ることも難しいでしょう。
チームや会社全体で中長期的に数多くの業務を進めていく上では、そのような状態を放置すると問題発生の可能性が上がります。結果として、トラブルの収束も含めた全体の工数を増大させかねません。
以下のような考えは視野を狭くしがちなので、要注意です。
・他の人よりも自分がやった方が早い
・他の人に任せたら良いものはできない
・自分の担当業務は、自分だけが把握していればよい
・自分にしかできない仕事があるから誇らしい
・他の人が自分と同じレベルに達するまでには時間がかかる
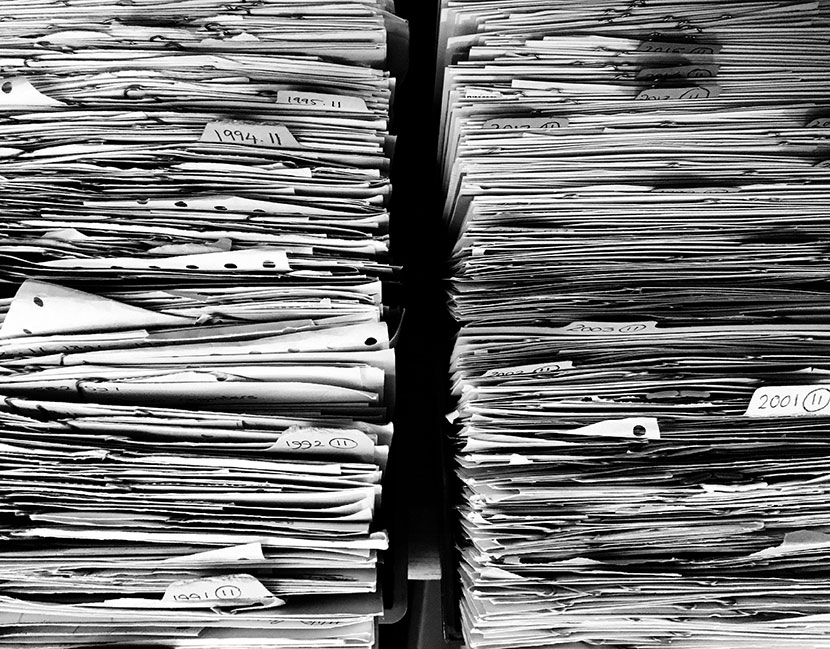
「良い属人化」をしよう
ここまでで「悪い属人化」について考えてきました。
思い当たるフシがある方もたくさんいると思います。
ただ一方で、こんな経験もありませんか?
「チームでやってみたら1人でやるよりも良い仕事ができた!」
「良い属人化」が実現されていると、属人化により全体の効率が上がります。
「属人化しているかも?」と言えるような専門性を持った人がいると、効率の良い業務の進め方や教育方法を考えやすくなるためです。 結果として、組織内での知識の循環、協力体制の構築を容易にします。
ここで属人化に適した業務の例を4つ挙げてみます。
A1・希少性の高い技術が必要な業務
A2・専門性の高い業務
A3・臨機応変に対応しなければいけない業務
A4・市場価値が高い業務
これらの業務を問題なく遂行するためには、豊富な経験や知見、業務に応じた高い問題解決能力が必要です。初心者が最初から対応できるものではありません。
まだ経験も知識も乏しい新人に、専門性の高い業務を任せることは組織としてもリスクとなります。
ある程度の属人化は覚悟の上で、業務に慣れた人間が予めマニュアルを作成するのは重要です。新人にはまず簡単でリスクの低い業務を与え、マニュアルも参考にしながら中長期的に必要な能力を養う機会を設けるのが良いと考えます。そして徐々にスキルアップしてもらえれば、やがてはマニュアルの作成を任せ、後進の教育にあたってもらうことなども可能となるでしょう。こうして組織内の知識の循環が可能となります。
組織にとっての「良い属人化」=「全体効率の最適化」を目指しましょう。
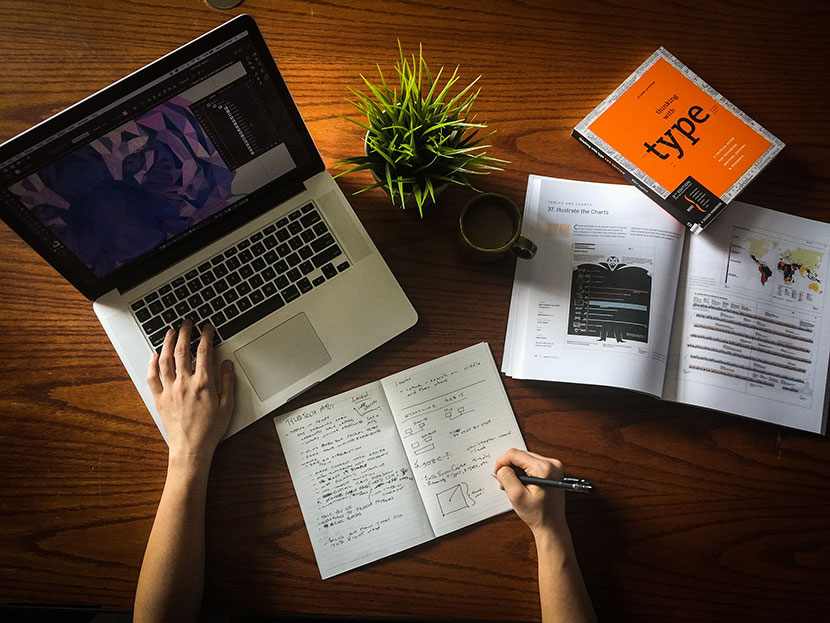
属人化に適さない業務
ちなみに、属人化に適さない業務の例はこちらです。こういった業務を属人化してしまうと全体の効率が下がります。
B1・簡単で作業手順に変化もないが、発生頻度が高いもの
B2・専門性が必要ないもの
B3・複数人による連携が必要なもの
B4・市場価値が低いもの
もはや古臭いたとえとなりますが、「会議用の資料を20部コピー、ホチキス留め」などを想像してみると分かりやすいのではないでしょうか。
この作業を1人で独占してもあまり意味がないですよね。
「良い属人化」のために業務を「分解」しよう
属人化に適さない業務と、属人化に適した業務の2種類がどのようなものか、大体分かってきたかと思います。
それでは「良い属人化」を実現するための実作業に移りましょう。
まずは、今の業務の中に「悪い属人化」がないか?を洗い出すのが大事です。
そのために業務を「分解」してみましょう。手順は以下のとおりです。
- 業務を細かなタスクに分け、時系列順に並べる
- 各タスクのコツ、工夫しているポイントを書き出す
- 各タスクのNGパターンも明記しておく
- フローにまとめる
業務を「分解」した後は、属人化に適さないタスクと適したタスクに仕分けます。
「業務」と「タスク」では単位が異なりますが、先ほど例に挙げた「属人化すべき業務(A1〜A4)」「属人化すべきではない業務(B1〜B4)」も参考に仕分けると良いと思います。
分解と仕分けまで終わると、それをベースに業務マニュアルの作成もある程度までは可能になっているのではないでしょうか。マニュアルを作成できれば引き継ぎの難易度が下がり、「悪い属人化」の発生率も下がります。
ちなみに、
・ローテーション制で担当を定期的に入れ替える
・定例MTGを開催し、複数人でルーティンを見直す
なども「悪い属人化」防止には有効です。

適度な属人化で専門性を伸ばす
なお、属人化すべきでない専門性の低いタスクは、経験の浅い人にどんどん引き渡すことで
「できないことをできる人を増やす」ことが可能になります。
「難しいことをいきなりやるのは大変だけど、簡単なことからならとっつきやすい」と言えば更に分かりやすくなるでしょうか。
新人には、まずは簡単なステップから始めてもらう。
先輩は、ある程度までの属人化は気にせず、専門性を身につけるべく業務に邁進する。ただし実際には1人で抱え込まず、知識の共有を心がける。
これも教育や知識の循環のため、組織全体の効率を上げるためには重要です。
また、他の人に業務を渡せると下記のようなメリットが発生します。
・渡した業務の分、時間を空けられるようになる
・属人化すべきタスクに集中できる
属人化すべきタスクにコツコツと集中していくと、個人の「専門性」が伸びます。
【属人】で仕事をする
最後に改めて「属人化」ではなく「属人」という言葉について考えてみましょう。
_____________________________________
(Weblio辞書より 情報提供元:三省堂大辞林第三版・Wiktionary日本語版)
_____________________________________
「人を基本にして考える」という行為の結果、「属人化」は生まれます。
「属人化」というとネガティブな話を多く聞きますが、「属人化」と「教育、専門性や全体効率の向上」は分かち難い間柄でもあることを、今回お分かり頂けたと思います。
属人化を過剰に恐れず、まず個人を基本として仕事を進めることが重要です。
初心者だけが一度に同じスタートラインに集まっても、全体効率の向上は達成しにくいのです。
中小企業ほど属人化を上手く利用しないと、人数、規模で大企業に勝てません。
しかし、「悪い属人化」が多くなると、チームで勝つこともできません。
日々の業務で忙しい中、時間を捻出するのも大変だとは思います。
でも、スキマ時間などを上手く活用し、業務の分解から試すことを提案します。
「この業務、無駄では?」「ここは2人体制にした方がいいかも」など、属人化以外にも気付くことがたくさんあるでしょう。
「悪い属人化」を無くした「必ず誰かが代打できる会社」は休暇なども取得しやすい、働きやすい会社とも言えます。
テレワークが盛り上がり多様な働き方が選べることがますます重要となるこの時代、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

